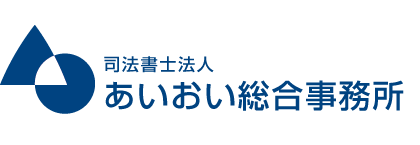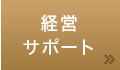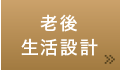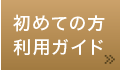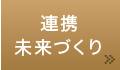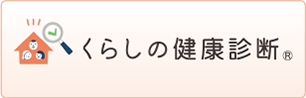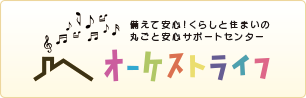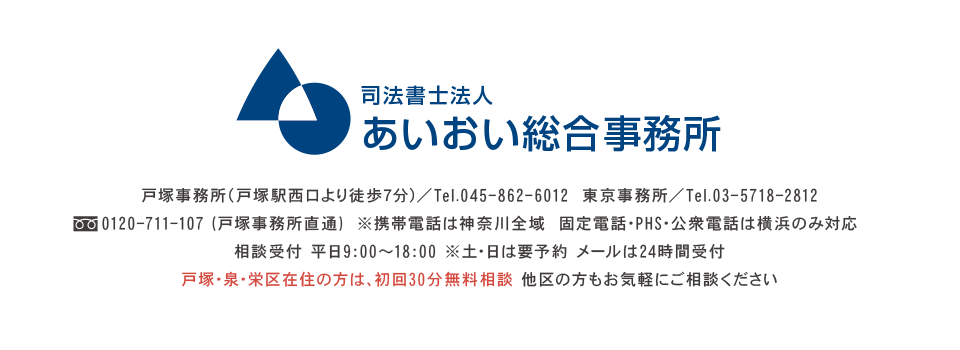くらしの法律情報
2025年10月15日 [くらしの法律情報]
相続手続きは「最初の準備」が重要 〜遺言・財産・相続人の確認から始めましょう〜

こんにちは!司法書士の清水です。
相続は一度で完結させるのが理想です。準備が不足すると、後から財産や債務・相続人が見つかり、遺産分割協議のやり直しが必要になることがあります。関係がこじれる前に、最初に全体設計を行うことが重要です。
公正証書遺言:公証役場で検索可能。内容が有効なら原則その指示に従います。
自筆証書遺言:法務局の保管制度の利用有無を確認。封書保管の場合は家庭裁判所の検認が必要。
自宅保管の遺言書:勝手に開封せず、適切な手続で有効性を確認します。
遺言の有無で進め方が大きく変わるため、着手前に必ず確認します。
金融資産:預貯金・株式・投信・保険などを網羅的に洗い出し。
不動産:登記事項・評価・利用状況を確認。
動産:車・貴金属・美術品等。
負債:借入・保証・未払い税金・医療費等。
漏れは後日の再協議を招きます。専門家は照会先の選定や証憑の集約で見落としリスクを低減します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定。
前婚の子や認知された子など、交流が薄い親族が相続人となることもあります。後日の判明は協議無効・やり直しの原因に。最初に確実に確定します。
銀行・証券会社の名義変更/解約:必要書類(遺言・戸籍・遺産分割協議書等)を先に整備し、一気通貫で申請。
不動産の相続登記(法務局):分割内容を反映して申請。登記完了を待って売却・活用の段取りへ接続。
税務署への相続税申告(原則10か月以内に申告・納付):評価・特例適用の検討→申告書作成→納付(現金/延納・物納の可否検討)までを期限から逆算して準備。
相続手続きは複数の窓口をまたいで行うため、どの順番で・いつまでに手続きするかを整理することが不可欠です。専門家と一緒に、全体を見渡せる“手続きの見取り図”を作れば、抜け漏れや期限遅れを防げます。
・相続は一度きりでも、制度は複雑。
・遺言の有効性確認と活用設計
・財産・負債の網羅的調査と証憑整理
・相続人確定(戸籍収集・関係説明図の作成)
・登記・金融機関・税務の期限管理と書類統一
司法書士(登記・手続設計)を中心に、税理士(評価・申告)と連携することで、抜け漏れと再協議のリスクを最小化し、円滑に完了まで伴走します。
1. 遺言の有無を確認(方針が決まる)
2. 財産・負債を網羅的に調査(後戻り防止)
3. 相続人を確定(協議の土台づくり)
そのうえで、期限を意識した全体の見取り図を専門家と作り、効率的に進めましょう。
相続は一度で完結させるのが理想です。準備が不足すると、後から財産や債務・相続人が見つかり、遺産分割協議のやり直しが必要になることがあります。関係がこじれる前に、最初に全体設計を行うことが重要です。
1.遺言の有無を確認する
公正証書遺言:公証役場で検索可能。内容が有効なら原則その指示に従います。
自筆証書遺言:法務局の保管制度の利用有無を確認。封書保管の場合は家庭裁判所の検認が必要。
自宅保管の遺言書:勝手に開封せず、適切な手続で有効性を確認します。
遺言の有無で進め方が大きく変わるため、着手前に必ず確認します。
2.相続財産の調査を徹底する
金融資産:預貯金・株式・投信・保険などを網羅的に洗い出し。
不動産:登記事項・評価・利用状況を確認。
動産:車・貴金属・美術品等。
負債:借入・保証・未払い税金・医療費等。
漏れは後日の再協議を招きます。専門家は照会先の選定や証憑の集約で見落としリスクを低減します。
3.相続人の範囲を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定。
前婚の子や認知された子など、交流が薄い親族が相続人となることもあります。後日の判明は協議無効・やり直しの原因に。最初に確実に確定します。
4.手続きスケジュールを組み立てる(期限を意識した進め方)
銀行・証券会社の名義変更/解約:必要書類(遺言・戸籍・遺産分割協議書等)を先に整備し、一気通貫で申請。
不動産の相続登記(法務局):分割内容を反映して申請。登記完了を待って売却・活用の段取りへ接続。
税務署への相続税申告(原則10か月以内に申告・納付):評価・特例適用の検討→申告書作成→納付(現金/延納・物納の可否検討)までを期限から逆算して準備。
相続手続きは複数の窓口をまたいで行うため、どの順番で・いつまでに手続きするかを整理することが不可欠です。専門家と一緒に、全体を見渡せる“手続きの見取り図”を作れば、抜け漏れや期限遅れを防げます。
専門家に任せるメリット
・相続は一度きりでも、制度は複雑。
・遺言の有効性確認と活用設計
・財産・負債の網羅的調査と証憑整理
・相続人確定(戸籍収集・関係説明図の作成)
・登記・金融機関・税務の期限管理と書類統一
司法書士(登記・手続設計)を中心に、税理士(評価・申告)と連携することで、抜け漏れと再協議のリスクを最小化し、円滑に完了まで伴走します。
まとめ
1. 遺言の有無を確認(方針が決まる)
2. 財産・負債を網羅的に調査(後戻り防止)
3. 相続人を確定(協議の土台づくり)
そのうえで、期限を意識した全体の見取り図を専門家と作り、効率的に進めましょう。